
放生津八幡宮さん
立派な鳥居!
※魚取社へ〜
海に続く路地
|

放生津八幡宮社殿の正面は、こちら〜
※
|

大きな石灯籠〜氏子船頭中
流石〜北回船の寄港地の面目躍如!!
※八幡フォント〜(鳩文字、私が名付けました)
ここにも健在!
|

嘉永元年銘〜
※奉納砲弾
説明は無し。。
日露戦争時分のでしょうか?
|

卯尾田毅太郎像
太平洋戦争中に行われた唯一の国政選挙、
昭和17年(1942)の第21回衆議院議員総選挙で
当選し空襲にて戦死されたとか
(Wikipediaより)
※
|

左から
乱石一方面積(切込みハギ)
と
玉石往復積(たまいしいってこいづみ)
玉垣や石灯籠も廻船船方中のもの。
※境内地は広い〜
|

宝物殿の扉には
漆喰で鳥居が〜
綺麗です。。
※霊枩殿(枩=松なんですね)
松並木が綺麗だったんでしょうか?
|

霊枩殿の頑丈そうな漆喰
窓の庇も意匠が細かい(職人のニヤリ)
※社殿は、大阪城西丸の修復に当たった
高瀬輔太郎(たかせ すけたろう)が
棟梁となり、文久3年に再建。
|

奈呉町釣方漁師連中寄進
弘化三年 矢野啓道作(当時19歳)
ケヤキの寄木造り
|
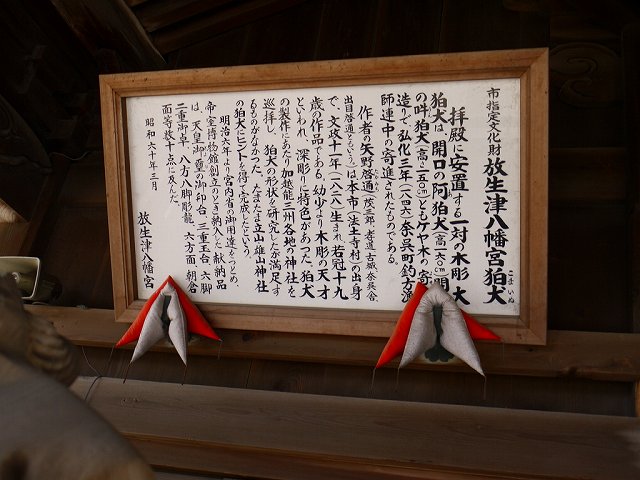
※
彫刻が綺麗です〜
|

狛犬というより
獅子ですね。
※深い彫が特長とか。。
|

阿(160cm)
※吽(150cm)
大きいですよ〜まだまださん
|

本殿社内には
右大臣左大臣
奉納馬も鎮座して〜
※絵馬は当り矢!
|

銅製奉納灯篭も大きい〜
※流石〜木彫りで有名な地区ですね。
|

龍も生き生きと〜
※
|

|

柱には装飾は無いですが〜
※堂下の土台は石組み
|

綺麗で堂々とした
姿形!
※
|

万葉の花
フジバカマ再び〜
※万葉歌碑
越中守大伴家持宿禰の歌
東風 いたく吹くらし 奈呉の海人の
釣りする小舟 漕ぎ隠る見ゆ
|

祖霊社
合祀された神様方
※アンチョコ〜^^;
|
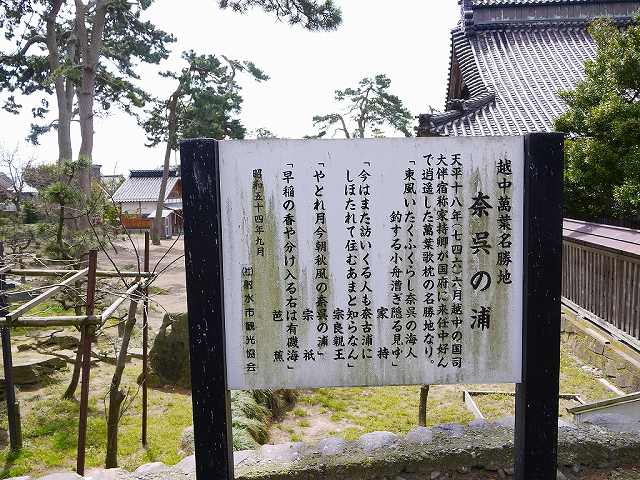
砂浜が沖に向かって
2kmも続いたとか〜
昔から風光明媚
だったんですね。
※石碑
|

ゴイサギが営巣中〜
|

※
|

手水鉢
※
|

ここの龍も負けじと…
※庇受けも〜
|

国旗掲揚台は
船のマスト??
※13基の曳山(花山車)が並ぶとか〜
|
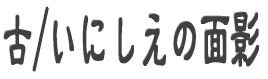 其の六百九拾九
其の六百九拾九